「寒いね。」
その少年の言葉に、少女は答えなかった。
兄弟なのか、友人同士なのか、それとも恋人同士なのかは判らない。
旅行なのだろうか?しかし、どう見ても中学生とおぼしき彼らが、二人きりでこんなところにいるのは、不自然な気もする。
だが、まわりを行く人たちはそんなことは気にも留めず、ただ流れのままに歩いていく。
ここは京都。日本という国の中枢が関東圏へと移り変わっていっても、いまだ千年王城としての陣容を誇り、何より日本人の心に深く残っている、そんな街である。
先ほど少年が「寒い。」といったのも無理はない。いつしか空からは白いものが舞い降り始めていた。それは少年たちが初めて見る"雪"であった。
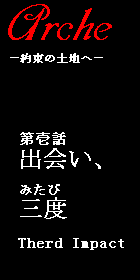
その日、京都は記録的な大雪に見まわれていた。
もっとも雪が降ること自体が久方ぶりのことである。何しろ、この前積雪が記録されたのは、実に15年以上も前のことになるのだから。
当然、生まれてからまだ15年しか立っていない少年たちにとっては、初めて体験することである。
雪どころか寒さ、冬ということ自体が初体験になる。つい3ヶ月ほど前まではこの国には『四季』、というものさえなかったのだから。
日本から四季が失われた、その原因となったのが15年前におきた『セカンド・インパクト』と呼ばれる未曾有の大災害である。
一般的には、南極大陸への大質量隕石の落下がその原因と言われているが、真相は『使徒』と呼ばれる謎の存在が関連し、人為的に起こされたものである。そう、未曾有の大災害は人類自らの手によって起こされたことだったのだ。
しかし、多くの人々にとって大切なのはその原因よりも結果であった。何より生き残るのに精いっぱいで原因を追求する余裕などはなかったのだ。そして、夏だけを残し、日本から季節は消え去った。
皮肉なことに四季が戻ってきたその原因もまた、『サード・インパクト』と呼ばれる大災害であった。
無論、その真相はまた人々に知らされることはなかった。今度もまた、人はその日を暮らしていくことに精いっぱいだったから。
好意的な見方をすれば、過去を振る返るよりも、未来を創っていくことを選んだからとも言える。痛みを忘れ生きていけるということは、人の愚かしさでもあると同時に、なにより強さの証であるのだから。
そんなだから。真相を知る人間たちが、普通の生活に戻っていくことにも、何ら支障はなかった。そして真相を知る者たちは『セカンド・インパクト』が始まりに過ぎなかったということも、『サードインパクト』がすべての結末であり、次の未来への始まりだということも知っていた。だから、彼らは生きる道を選んだ。普通の人間として。
そして軍も、ゼーレも、ネルフも、この世から消滅した。
その3ヶ月前、第3新東京市跡。
「気持ち悪い・・・」
惣流アスカははき捨てるようにそう言い放った。
その彼女の上で、少年-碇シンジ-はただ鳴咽をあげるだけで、その彼女の言葉に答えようとはしなかった。
ほんの少し前、シンジはアスカを絞め殺そうとしていた。何がシンジを駆り立てたかは、本人にも判らない。ただ衝動的にアスカの首を絞めていた。
しかし、それが成し遂げられる前に、アスカが意識を取り戻した。するとシンジの目から止めど無く涙が流れてきた。
そしてアスカはシンジを拒絶した。
二人の間に静寂が流れた。
「無事だったか。」
沈黙を破ったのは第3の人物であった。
「冬月・・・さん。日向さんに、青葉さんに、マヤさんも・・・。」
この状況を見て、はたして無事、と呼んでよいものかは疑問ではある。だが、傷ついてはいるものの、彼らは確かに"生きて"いた。
「あの、他の人は・・・?」
遠慮がちにシンジが尋ねる。先ほどのこともあってか声に覇気はない。もっとも、この状況を見て元気になれる者はそうはいないだろう。
それはさながら地獄のような光景であった。かの預言書にある黙示録の戦いが実際に起きたなら、おそらくこんな光景になるのではないだろうか。
空は真っ赤に染まり、海には、いやこのオレンジ色の液体−LCL−で満たされたものを海と呼ぶのが妥当かどうか判らないが。エヴァシリーズとリリスの残骸が散らばっている。その海は果てしなく広がり、そこに動くものの気配は感じられない。
この光景を見れば、シンジでなくともこの地球上に、自分たち以外に生きているものはいないのではないかと思えてしまう。
だが、
「心配はいらない、やがてみんな戻ってくるさ。人のカタチでな。それがシンジ君の望んだ世界なのだから。」
LCLの海の中でのことを、冬月は全て知っているようであった。
思えば、ネルフの中でも、冬月とゲンドウだけははじめから人類補完計画の全容を知っていた、だから、LCLの中でシンジが見たものを知っていても不思議ではない。
いや、もしかするとはじめから判っていた、という方が正しいかもしれない。
「じゃあ、ミサトさんや、リツコさんや、・・・父さん、も、無事なんですね?」
だが、冬月は哀しそうに首を振る。
「生きて行こうとする意志があれば、誰でも戻ってこれる。だが、それは生きているものだけだ。」
しばしの間があり、シンジは言葉を紡ぎだした。
「死んだんですね、みんな。」
悲痛な宣告に、しかしシンジは取り乱すことはなかった。冬月たちが驚くほどにシンジは落ち着いていた。
けれど、先刻アスカを殺そうとしたのも、またシンジである。
端から見るほどにシンジの内面は安定していないのかもしれない。
でも、
「シンジ君、変わったわね。なんだか、ほんの僅かな間に大人になったみたい。」
というマヤの感想が、ここにいるみんなの、共通の思いだろう。シンジとアスカを除いて。
この間、アスカは一言も口をきいていない。
だが、それに気付く者はいない。
サードインパクト、その引き金ともいうべきゼーレとの戦い。その前まで、彼女は心を閉ざしていた。
戦いの中、弐号機の中で自我を取り戻し、変な話だが,"元気に"戦っていたのは判っていても、全快ではないという意識があるからである。
そしてなにより、ここにいる誰もが、元気なアスカの姿というものを,"直接"見たわけではないのだ。
だから、シンジの微妙な変化には気がついても、アスカの状態にまで意識が向かなかったのである。
それが、アスカにとっての不幸の始まりであったことに、この時、誰も気付いてはいない。
「生きて、いかなければならないんですね。僕たち。」
つぶやくような、けれど確かな、シンジの言葉。悲観的な言葉の内容とは裏腹に、その瞳には決意が見える。
「そうだ。それも死んだ者たちの為、などという消極的な理由の為ではない。」
「私たち自身が、幸せになる為、ですね。」
そのシンジのつぶやきを、冬月とマヤがつなぐ。
「さしあたっては、世界の復興ですか。」
「また、忙しい毎日かぁ。」
そういう日向と青葉の表情もなぜか晴れやかである。
人類補完計画。ゼーレと碇ゲンドウがそれそれに進めていた、人が次のステップに進む為の、人という種が生き延びていく為の計画。
彼らの思惑からすればこの計画は失敗であったのであろう。
だが、個人個人の心は、確かに生きていく意志を持ち始めていた。
人が人であることを選んだ、その証として。
人類は確かに補完されたのかもしれない。"種"としてではなく、"個"として。
3ヶ月後。旧ネルフ本部。
第三新東京市はなくなっても、ここだけはなんとか原形をとどめていた。
不思議なことに、世界を満たしていたLCLが消えていくと、リリスも、エヴァシリーズも跡形もなく消え去っていった。
LCLの消えた後には山のような瓦礫、廃虚。だが、この惨状の割に死者は少なかった。まあ、行方不明者は多かったが。
真相を知る人間たちは、もっともシンジたちを含め極少数の人間だが、行方不明者たちが、生きるのを放棄した者たちだということを知っている。
だが、そのことも含め、事件の真相について冬月は公表するつもりはなかった。
生きることを選んだ人たちに、今更余計な不安を与えることはないし、自ら生を放棄したような人間に、かまっている暇もないのだ。
それに、冬月自身、どこかで、この件については終わったという、意識があるからなのも間違いない。
この3ヶ月、事後処理に追われ、その中で軍とゼーレの消滅を確認したせいもあるだろう。ゼーレの老人たちが"生きる"道を選ばなかったことを。
だが、今一つ理由がある。
今となっては冬月のみが知る事実があった。ゼーレとも、使徒とも違う脅威。
いまだその影すら、冬月は掴めていなかったが。
今の冬月にとってはそちらの方が問題であったのだ。
そして、冬月は決断する。
「また、シンジ君には辛い想いをさせてしまうな・・・」
うめくようにつぶやくと、冬月はゆっくりと顔を上げた。
「特務機関ネルフは、今日をもって解散する。」
ネルフの全職員−といってもシンジやアスカ、冬月自身を含めてわずか十数人だが−を前に、冬月はそう宣言した。
しばしの喧騒はあったが、そこに動揺はない。職員たちにしても、予測できた事態だからある。
サードインパクトの事後処理という雑務がなければ、3ヶ月前の時点でそうなっていたはずだからだ。
事実、少数の者以外は、すでに新しい生活に入っている。ここに残っている者の方が少数派なのだ。
「君たちの以降の生活については政府に約束をさせた。普通の人間として、生きていきたまえ。」
この3ヵ月の中で、それが冬月がもっとも心を砕いたことであった。すべてが終わった後、残されたものには平穏な生活を、冬月がゲンドウやユイに誓ったことである。
シンジを含めて・・・
だが、そんな想いとは裏腹に、シンジには、シンジだけにはまだ、戦いが待っているという事を、冬月だけは知っていた。
「副司令、いえ、司令代行はどうなさるおつもりですか。」
不意に表情を曇らせた冬月を見て、怪訝そうにマヤが尋ねる。
「私は、ここに残ろうと思う。」
「司令代行・・・」
ネルフの副司令、いや、ゲンドウ亡き後の司令代行として、ネルフ本部を見守っていくつもりなのだ。その場にいた全員がそう考えた。
その想いに水を差すこともない。誰もがそう思う。
やがて、職員たちは冬月と挨拶を交わすと、一人、また一人とネルフ本部をあとにしていった。
最後に残ったのは冬月とマヤ、アスカ、そしてシンジ。
「僕も、ここに残ろうかと思います。」
『もう帰るところもないから。』
シンジはそう続けた。最後までこの場に残った、これがその理由。
ともすると投げやりな言い方だが、別に世を儚んでいるわけでも、何かに絶望しているわけでもない。シンジが3ヶ月考えて出した、それが答えだった。
「なぜ?行くところがないなら私と一緒に来ればいいじゃない。アスカも、一緒に。」
シンジとて、そのことを誰にも相談しなかったわけではない。
そして、相談した結果、返ってきた答えは今のマヤの言葉と同じであった。マヤからも青葉からも、日向からもそう言われた。
だが、シンジの考えは変わらなかった。シンジがこの場に残ることを選らんだのは、死んだ父、ゲンドウを知りたかったから。彼が命を懸けたものを知りたかったからである。
すべては、結局、最後まで分かり合えなかった父への想い、ここに残ることで父の遺志を継ぐという想い、それに起因していた。
青葉も日向も、そんなシンジの意志を尊重した。
マヤだけが、この場に残ったのは、もう一度シンジを説得しようと思ったのは、彼女が女性だからであろう。
女性の持つ"母性"ゆえに、"姉"として、"弟"を放っておけない。そんな気分なのだ。
「父さんの、遺志を継ぎたいんです。ここにいればそれが判るような気がして。」
シンジの答えは一貫している。それゆえに決意の固さが感じられた。
「碇の遺志を、継ぐ気なら・・・ここへ、行くといい。」
シンジとマヤのやり取りを黙ってみていた冬月が、そう言ってシンジに一枚の紙切れを手渡した。
「これは?」
そこに書かれていたのは、一つの住所と、一人の女性の名前だった。
シンジはその女性の名前を知らなかった。
「加持君から、いや、碇から預ったものだ。事が済んだら、これをシンジ君に渡して欲しい、と。」
「父さん、が?」
「ここにはシンジ君の場所がある。碇はそう言っていたよ。」
「僕の居場所?それはどういう事です?」
「全てはそこに行けば判る。それと碇から一言、シンジ君にも、その女性にも、済まない、と。君から彼女に伝えてやってくれ。」
自分に未来を選ばせるため。ここに残って人生を浪費させないため。そんな想いから冬月が嘘をついているのでは、シンジはその可能性を考えた。
だが、シンジには冬月の言葉に嘘は感じられなかった。何より、父の遺志が感じられれるような気が、シンジにはした。
純粋に、ゲンドウの残した"居場所"という言葉の意味と、顔も名前も知らないその女性に、興味があったからかもしれない。
だから、冬月の言葉に素直に従う気になった。
「アタシも、一緒に行くわ。」
不意にアスカがそう言った。
この3ヶ月の間、アスカはほとんど口をきかなかった。特にシンジとは。
シンジとしても、自分の非を認めてはいる。
だから、彼女が自分を拒絶するのは、当然だということも。
ここに残るといいだした理由も、一つはそこにあった。
アスカとは、もう一緒にはいられないだろうから。
「なによ、その顔は。アタシが一緒じゃ不満なの?」
「そ、そんなことないよ。嬉しいんだ。一緒に来てくれて。」
正直シンジは嬉しかった。まだアスカと一緒にいられることが。
ずっと一緒にいたい。だが、その可能性を自分自身で壊してしまった。だからここに残ることで、自分自身に罰を与えようとしていた、いや現実から逃げようとしていた。
つまりは、自分はアスカが好きなのだ。シンジはそう自分自身の気持ちを解釈した。だから純粋に嬉しいのだ。そんな風に。
少なくともこの時点では、シンジは自分の気持ちをそう信じた。いや、信じようとした。
アスカもまた、正直嬉しかった。だが、彼女にはまだ、わだかまりがある。
自分がシンジのことを好きだという気持ちに、疑いも、曇りはない。ただそれを当人か素直に認められるかどうかである。
だがシンジはどうなのだろうか。シンジが自分の首を絞めたその理由、シンジさえ気付いていないシンジの心の中の何か。それがアスカには引っかかっていた。
結局それがある為に、シンジの言葉を信じきれないのだ。
一緒に行くといった理由も、怖いから。側にいなければシンジは自分のことなど忘れてしまうのではないか、という想いがあるからである。
けれど、希望はあった。本当なら二人きりで新しい生活を、というのが望みであったが、それでもシンジの側にいられることには違いない。
ずっと側にいれば、いつかシンジを心から振り向かせることができる。アスカにはその自信があった。
明るい未来を信じる。それはここで戦ったものすべての、共通の想い、願いでもあった。
「じゃあ、冬月さん、マヤさん、お世話になりました。」
一度決断をしたら、行動に移るのは早かった。シンジとアスカは手を取り合い、歩きはじめる。
そして、少年と少女は旅立っていった。この先に待つ未来に、希望があることを信じて。
「3度目の出会い、か。」
去っていく二人の後ろ姿を眺め、冬月はつぶやいた。
「3度目?」
マヤに問われ、冬月は振り向く。
「伊吹君はどうするのかね。」
不意に話を変える冬月。まるでこの件について追求されたくないかのように。
「まだ、判りません。シンジ君には偉そうなことを言ったけど、私にだっていくアテがあったわけじゃないですから。」
そんな冬月の気持ちを察してか、突然の問いにマヤは素直に答える。
そして、しばしの沈黙の後、
「シンジ君は、過去に2度、彼女と出会っている。」
そう言って冬月は静かに語りはじめた。マヤにとっては不幸であったかもしれない話を。
・
・
「無責任な言い方かもしれんがな、私たちにはどうすることもできん。」
「シンジ君が彼女に会わなければ、それで済む話じゃないんですか?」
「そうだ、だから我々はあの二人を引き離した。2度も、だ。」
「じゃ、なぜ今になって。このまま出会わずに、このまま生きていった方が幸せだったじゃないですか。それに・・・」
口調こそ冷静であったが、マヤの声はショックと、そして怒りとで震えていた。それがなにに対する怒りなのか、彼女自身も知らないままに。
「碇の、遺言だからな。」
「でも!でも、これじゃあまりに・・・。アスカだって、可哀相です。」
「強要するわけではない。全ては、シンジ君が選ぶことだ。アスカを選ぶか、彼女を選ぶかそれを含めて、な」
「でも・・・」
納得できないマヤ。
「2度も引き離しておいて、なぜ司令は最後にこんなことを・・・?」
一呼吸おいて、マヤは尋ねた。
「それが、ユイ君の本来の望みだったからだ。」
「ユイさん・・・、シンジ君のお母さんですね。でも、どうして?」
「大人の身勝手、と言ってしまえばそれまでかも知れん。だが、我々は信じたかったのだよ、子供たちを。」
「信じる・・・」
「そうだ、見えない影に怯えて生きていくより、見えない影と対決する強さを。その強さを持って未来を創ってくれることを。」
「それをまた、シンジ君に託すんですね。」
「シンジ君に押し付けた、ということになるのだろうな。たしかにシンジ君には人より過酷な運命が待ち受けているかも知れん。だが、大人が子供に未来を託すのは間違ったことではない。これも、言い訳かな?」
マヤは一つ大きく息をついた。
「未来も平和も、命がけで護っていかなきゃいけないんですよね。シンジ君じゃないけれど、逃げては駄目だから。でも・・・」
ほんの少し、恨めしそうな視線を冬月に向ける。
「でも?」
「こんな話を聞かされたら、とてもじゃないけど普通の生活になんか戻れませんね。」
だが、口調こそ恨みがましいが、その表情は曇ってはいない。マヤにしてみれば、シンジが苦悩しているのを知らずに、一人幸せに暮らしていたら、間違いなく後悔し、良心の呵責に苛まれていただろう、という想いがある。
むしろ、この話を聞かされたことを、感謝しているといってもいい。
そんなマヤの気持ちを見越してか、冬月は微笑みながら言った。
「すまんな。青葉君や日向君にもそう言われたよ。」
冬月は既に青葉や日向もこの事実を知り、動いていることを告げた。そして二人がマヤにだけはこの事実を告げないように、彼女には平穏な人生が送れるように、と冬月に頼んでいたことも。
「結局は、君も巻き込んでしまったがな。」
「一人カヤの外、よりはマシです。」
そう言ってマヤは微笑んだ。
なんとなく、マヤにもユイの気持ちが分かるような気がした。
未来は、信じる者のみに与えられるものなのだ。そして子供に託す、ということは、大人が何もしなくてよい、ということではない。
シンジの境遇に同情し、運命を呪う前に、まず、自分がやれることをやろう。マヤはそう決意した。
そしてシンジたちなら必ず困難を乗り越えていける、とマヤは信じることにした。
それが楽観であり、それこそが大人の身勝手だということも理解していたが、信じることが勝利の為の第一歩だということも、彼女は知っていたからである。