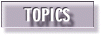<長唄の歴史と由来>
長唄は17世紀末頃、江戸に生まれた歌舞伎音楽、いわゆる「江戸長唄」として
発達した、三味線音楽です。歌舞伎芝居や、華やかな舞踊の伴奏音楽として発展
していきました。その後、幕末になると歌舞伎から離れた純粋な演奏用としての
「お座敷長唄」が生まれました。この様に多種多様に表現の幅を広げていった音
楽といえます。
<長唄の音楽的特徴>
長唄はいわゆる「うたもの」といい、洋楽に例えれば歌曲に近い音楽といえます。
情景や情趣を美しい旋律にのせて唄い表現されています。
大まかに分けて長唄には3種別の音楽的作風があります。代表曲を上げますと、
の「秋の色種」などがあります。
長唄の歌舞伎での役割として見逃せないのは、「黒御簾(くろみす)下座 音楽」
です。
舞台下手(向かって左側)に格子状に御簾がかかっている所があります。その御簾
の内で芝居に合わせ、唄・三味線を演奏したり、色々な効果音を演奏します。役者
のセリフに合わせ情感を表現する唄や三味線演奏、お囃子の太鼓で雨・風音を表現
したり、幽霊の出るドロドロなどの効果音を出したりとBGMの役割もあるのです。
<長唄の演奏形態>説明文の下に簡略図があります。
ここでは良く知られている義経・弁慶主従が安宅(あたか)の関を通る「勧進帳」
を例にあげてみます。長唄三味線が活躍する代表的な演目です。
「勧進帳」は能の謡曲「安宅」を元にし、舞台中央の背景に松を描いた松羽目物の
最初の作品といわれています。その松羽目の前に「長唄囃子連中」(ながうた
はやしれんじゅう)として「地方(じかた)」(役者に対し演奏する奏者を
そう呼ぶ)が並び演奏していきます。
まず、緋毛氈を掛けた山台を設け、舞台に向かって左に唄、右に三味線と一列に
並びます。又、この作品には「出囃子」(でばやし)といってお囃子が付き、
唄・三味線の前(山台前下)に並びます。このような演奏形態を総じて「出囃子」
と呼びます。「鏡獅子」などの舞踊音楽でもこの形をとります。「出囃子」の場合、
唄の中央の人を「タテ唄」、三味線の中央の人を「タテ三味線」と呼びます。
タテとは、その曲をリードしていくコンサートマスターの役割を担っています。
以下左右対称に「ワキ唄」「ワキ三味」「三枚目」…と順に並び、最後の人は
「トメ」と呼び、曲をしめる重要な役をもっています。この枚数は作品によって
異なり、勧進帳では三味線8挺(三味線を舟に例え数える単位)、唄8枚の<8挺
8枚>の編成になります。お囃子は舞台左から太鼓、小鼓・笛と並び、やはり作品に
よって笛以外は人数も異なります。勧進帳では大鼓1・小鼓5・笛の編成で総勢
23人の大合奏で華やかな演奏になります。
作曲者:四代目 杵屋 六三郎
初 演:天保11年(1840)
河原崎座、三月狂言、七代目市川團十郎が初代市川團十郎190年祭として上演。
勧進帳は唄が物語を進行させていく、抒情詩の世界です。弁慶の勧進帳読み上げ
は、あまりにも有名です。判官富樫との問答の緊張感や立ちまわりなど、音楽と
芝居、舞踊でわかりやすく表現されています。最後の花道での弁慶の「飛び六法」
は大向こうの声も沢山かかるワクワクする見せ場です。ここでも太鼓と笛が
「黒御簾」で音楽をつけ盛り上げます。
又、長唄とは関係がないのですが、舞台上手(向かって右)では「つけ打ち」
といって役者がミエをきる時、花道へ引っ込む様に合わせる効果音もつきます。
このつけ打ちの役は大道具さんが担当します。
歌舞伎舞踊の長唄は、芝居進行・人物の情感表現・舞踊伴奏・効果音と芝居の要
として作られているといえます。
そもそも歌舞伎って?
1603年、京都の四条河原(現南座のある辺り)で出雲のお国が念仏踊りを唱
えたことが、歌舞伎の始まりとされています。
歌舞伎の語源は傾く(かぶく)からきているといわれています。戦国時代が去り、
平和な徳川の時代(まだ鎖国もされていなかった慶長年間)、他国からの輸入品
もあり、新しいファッションや自由な精神がいきづいていた頃、そういう人物達
のことを傾いた人達、傾き者と呼ばれ、現代風な・当世風な形容のされかたをして
いたらしいのです。この傾くという動詞がなまって名詞になり歌舞伎となったそ
うです。歌(音楽)舞(踊り)伎(技)の三要素の入った、新しい時代の先端を
担った芸術といえるのでしょうか。